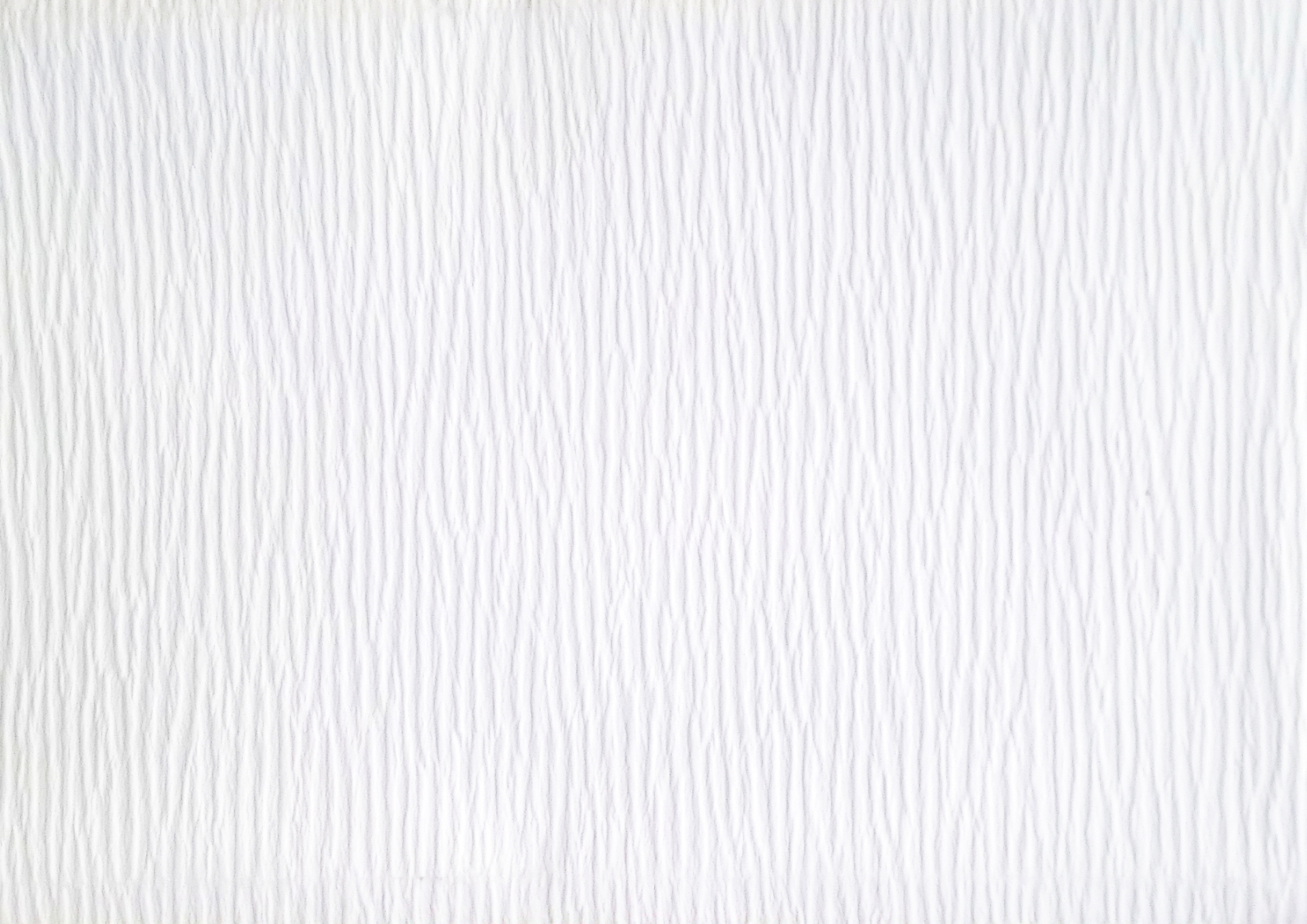(本ページにはプロモーションが含まれています)
近年日本の漫画などが海外でも人気ですが、明治時代にも海外で喜ばれた書物がありました。『ちりめん本』(英:Crepe Paper Books)という、多色の挿し絵と欧文が木版刷りされた和紙をちりめん状に加工し和綴じ製本したもので、しっとり柔らかい手触りでとても美しく、現在では美術品としての価値も高まっています。
明治17年に長谷川弘文社という出版社を立ち上げた長谷川武次郎(はせがわ たけじろう)によって刊行されました。もともとは日本の子どもの語学教育のためのテキストとして考案されたものでしたが、当時ヨーロッパは浮世絵に影響されたジャポニズムと呼ばれる日本ブームの最盛期。浮世絵画法の挿し絵が使われた美しい工芸品であるちりめん本は日本土産として好評を博し、後には海外の出版社とも共同出版するなど、結果的に日本の文化を他国に紹介する役目を帯びていったようです。
ちりめん本の代名詞ともいえる有名な「日本昔噺」シリーズ(英: Japanese Fairy Tale Series)は、「桃太郎」「舌切雀」「猿蟹合戦」「花咲爺」「かちかち山」など、日本の古くから伝わるおとぎ話を題材とした20巻21冊(No. 16の「鉢かづき」が後に「分福茶釜」に差し替えられた為1冊多い)のシリーズで、明治18年から明治25年に刊行されました。英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語版などが出版されています。
長谷川武次郎に協力して翻訳を行った在日欧米人には、アメリカ合衆国長老教会宣教師のデビッド・タムソン、同会の宣教師、医師でヘボン式ローマ字の開発者として知られるジェームズ・ヘボン、著名な日本研究家のB.H.チェンバレン、チェンバレンが親しくしていた英国海軍兵トーマス・ジェイムズの妻ケイト・ジェイムズ、アメリカの出版社の通信員として来日し、後に帰化して「小泉八雲(こいずみ やくも)」として知られることになる作家ラフカディオ・ハーンらがいました。挿絵画家には小林永濯(こばやし えいたく / 画号:鮮斎永濯 せんさい えいたく)、鈴木華邨(すずき かそん)などの一流の日本画家の名が並んでいます。
この「日本昔噺」シリーズは続編(No.21~25)や番外編の「竹取物語」、第2シリーズ No1~3と続きました。続編のNo23~25は小泉八雲の著作で、これらに別の2冊を合わせ、小泉八雲作品を集めた5冊セットでも刊行されています。ちりめん本人気は昭和初期頃まで続き、「日本昔噺」シリーズ以外にも日本の文化を紹介したものやカレンダー、観光案内や、長谷川弘文社以外の出版社から発行されたものも存在します。
現在では価格も高騰傾向で手軽には入手しづらくなっていますが、博物館展示やデータベースなどでその魅力に触れることができます。
■国際日本文化研究センター ちりめん本データベース